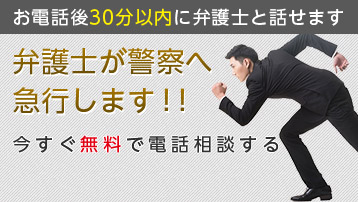逮捕後、不起訴でも前科がつく? 前科をつけないための3つのポイント
- その他
- 逮捕
- 不起訴
- 前科

令和4年4月、兵庫県姫路市白浜地域の公共事業を巡って市職員に不当要求を繰り返した容疑で書類送検された姫路市議について、神戸地検は「不起訴」としました。この判断について神戸地検は「収集した証拠では事実を認定できない」とコメントしています。
刑事事件の行方を報じるニュースや新聞などでは「不起訴」という用語が登場することがあります。ご自身やご家族が逮捕されてしまった方としては、不起訴と「前科」の関係が気になるものでしょう。
本コラムでは、「逮捕されたあとで不起訴になったとき、前科はどうなるのか?」という疑問について、ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士が解説します。
1、「逮捕された」=「前科がついた」ではない
警察に「逮捕」されたからといって、必ずしも「前科」がつくわけではありません。
逮捕と前科はイコールではないのです。
-
(1)逮捕された段階は「疑い」があるだけ
「逮捕」とは、罪を犯した疑いのある者について、逃亡や証拠隠滅を防ぎ、正しい刑事手続を受けさせるために自由を制限する強制処分です。
逮捕されたのには容疑をかけられるだけの理由や必要性はあるものの、逮捕された段階では、まだ「犯人」として扱われません。 -
(2)前科がつくのは「有罪」になったときだけ
「前科」とは、裁判で有罪判決を受け、刑が確定した経歴を指すものです。
わが国の刑事制度では「推定無罪の原則」が採用されています。
これは「有罪判決が確定するまでは無罪と推測される」という考え方です。
したがって、有罪判決が確定するまでは犯人ではありません。 -
(3)「不起訴」の場合は前科がつかない
「前科」がつくのは、刑事裁判が開かれて裁判官から有罪判決を受けたときだけです。
したがって、刑事裁判で無罪判決を受けた場合や、そもそも刑事裁判が開かれなかった場合には前科がつきません。
刑事事件の基本的な流れとして、まずは被害者からの被害届の提出を受ける等して、警察が捜査を進めて、犯罪の容疑がある被疑者を取り調べます。
その後、事件は検察官へと引き継がれて、検察官が刑事裁判を起こすべきかどうかを判断します。
このとき、さまざまな事情を考慮したうえで、「刑事裁判は見送る」という判断が下される場合もあります。
これが「不起訴」です。
逮捕されたとしても、検察官が不起訴を選択すれば、前科はつきません。
2、まぎらわしい「前科」と「前歴」の違い
「前科」と紛らわしいのが「前歴」です。
前述のとおり、前科とは、「裁判で有罪判決を受け、刑が確定した経歴」のことを意味します。
一方で、「前歴」とは、「警察や検察などの捜査機関から犯罪捜査を受けた事実」のことです。
捜査機関では「犯罪経歴」という情報を管理しており、刑事裁判の結果にかかわらず記録されています。この記録が、「前歴」と呼ばれているのです。
刑事裁判で無罪判決を受けた場合や検察官が不起訴を選択した場合にも、それに関する情報は前歴として記録されることになります。
ただし、前歴は捜査機関が厳格に管理しており、外部に漏れることはありません。
また、事件の事情を知っている参考人として事情聴取を受けたという程度では、前歴としては記録されません。
3、逮捕後に不起訴を得るためにするべきこと
犯罪の容疑をかけられて逮捕されても、検察官が不起訴とした場合には前科がつきません。
つまり、前科がつく事態を避けるには「不起訴を得ること」が大切です。
-
(1)不起訴には「理由」がある
検察官が下す不起訴にはさまざまな「理由」があります。
主な理由は、以下の三種類です。- 嫌疑なし ほかに真犯人の存在が明らかになった、アリバイがあるなど犯罪の実行が不可能であることが証明されたなど、犯罪の容疑が完全に晴れた場合に選択される処分です。
- 嫌疑不十分 ある程度の疑いは残るものの、犯罪の実行を証明するためには証拠が不十分である場合の処分です。
- 起訴猶予 犯罪の実行を証明する証拠は十分で、起訴すれば有罪判決が下されるだけの状況はあるものの、諸般の事情を考慮して「あえて起訴しない」という処分です。
冒頭で紹介した市議が不起訴になったケースも、嫌疑不十分でした。
令和3年版の犯罪白書によると、不起訴になった人員の総数15万2569人のうち、全体の69.5%にあたる10万5986人が起訴猶予となっています。
次いで多いのが嫌疑なしと嫌疑不十分で、合計は22.0%にあたる3万3539人でした。
上記の他にも、「親告罪における告訴の取り消し」「心神喪失」「時効完成」「被疑者死亡」などが、不起訴の理由として存在します。
しかし、これらの理由が当てはまる事例はまれです。
基本的には、不起訴を得るためには「起訴猶予」を目指すことがもっとも堅実だといえます。 -
(2)起訴猶予を得るには被害者との「示談」が有効
「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」となるのは、容疑が完全に晴れた場合や証拠が不十分であった場合のみです。
しかし、たとえ罪を犯したという事実があっても、不起訴とならないわけではなく、起訴猶予が選択される余地は残されています。
起訴猶予が選択される際に考慮されるのは、次のような事項です。- 被疑者本人が深く反省している、家族などによる監督強化が約束されているなど、再び罪を犯すことはないと思料できること
- 被害者に対する謝罪や弁済が尽くされていること
- 逮捕などの処分で被疑者本人が社会的制裁を受けていること
これらのうち、「被害者に対する謝罪や弁済が尽くされていること」は、容疑をかけられている者に積極的に努力する余地があります。
裁判などの法手続きの外で謝罪や弁済を尽くして許しを請うことを「示談」といいます。
被害者が謝罪を受け容れて和解に至れば「示談成立」となります。
重大な被害を生じさせた事件では、「深く反省していても許されるべきではない」「謝罪や弁済を尽くしても社会の非難は免れない」といった判断が下されることもあります。
しかし、被害者との示談交渉を進めて許しを得ることで、検察官が起訴猶予を選択する可能性を高めることはできます。
したがって、不起訴を目指すならまずは被害者への謝罪や弁済を最優先するべきなのです。
4、前科をつけないための3つのポイント
刑事事件を起こして逮捕されても、必ず前科がつくわけではありません。
以下では、「前科がつく事態を避けたい」と望む方が取り組むべきポイントを紹介します。
-
(1)直ちに弁護士に相談する
刑事事件を個人の力だけで解決するのは困難です。
まずは、弁護士に相談することを検討してください。
弁護士は、依頼主の代理人として被害者との示談交渉や捜査機関・裁判官へのはたらきかけ、刑事裁判における弁護活動などをおこなうことができる、唯一の存在です。
法律の知識と刑事事件の実務経験にもとづいて、もっとも穏便な解決を実現するための弁護活動を尽くしながら、警察や検察官による不当な捜査に対抗することもできます。
ドラマなどフィクションの世界では、法廷で検察官と言い争う描写ばかりが目立ちますが、実際に弁護士が活躍するのは法廷の外です。
特に、前科がついてしまう事態を避けるためには、刑事裁判に発展する前にさまざまな弁護活動を尽くす必要があります。
まずは弁護士に相談するようにしましょう。 -
(2)逮捕されるよりも前に解決する
警察により逮捕されたというだけでは、前科はつきません。
とはいえ、逮捕されて一般社会から隔離されてしまうことで、家庭や会社や学校における生活や評判に悪影響が生じてしまいます。
状況によっては、離婚や解雇や退学といった重大な不利益が生じることもあるのです。
罪を犯した事実があるなら、警察が捜査を進めて逮捕されてしまうよりも前に解決を図ることが最善です。
特に、被害者が存在する事件では、示談交渉を始めるタイミングが早ければ早いほど有利な結果が期待できます。
事件を起こした日から間をおかずに示談交渉を進めれば、被害者が警察に相談や届け出をするよりも前に事件を解決できる可能性があります。
迷ったり、ためらっていたりする間にも、警察が捜査を進めて逮捕へと近づいているかもしれません。
素早くアクションを起こすように心がけましょう。 -
(3)不起訴による解決を目指す
すでに警察に逮捕されている場合でも、諦めないでください。検察官が不起訴とすれば刑事裁判が開かれないので、刑罰を受けることも、前科がつくこともないのです。
前科をつけないためには、刑事裁判で争って無罪判決を得るという方法もあります。
しかし、検察官が有罪判決を得られる事件を厳選して起訴しているという状況では、無罪判決を得るのは実際には困難です。
前述のとおり、不起訴にはいくつかの理由がありますが、容疑をかけられている人による積極的なはたらきかけによって実現する可能性が高いのは「起訴猶予」です。
起訴猶予を実現するためには「深い反省を示す」「被害者との示談を成立させる」「再び罪を犯すことがないよう誓約して環境を整える」などの行為が必須になるので、弁護士にサポートを求めましょう。
5、まとめ
罪を犯したことが事実でも、検察官が不起訴と判断すれば、前科はつきません。また、警察に逮捕されたとしても、逮捕されただけでは前科はつかないのですから、逮捕されてしまったからといって、諦めないでください。
前科は資格や就職等に関わるというだけでなく、そもそも前科が付くのを避けられるのであれば避けたいのが切実な心情のはずです。
刑事事件を起こしてしまい、容疑者として逮捕されてしまった場合には、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が、スタッフと一丸になって、全力でサポートします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています